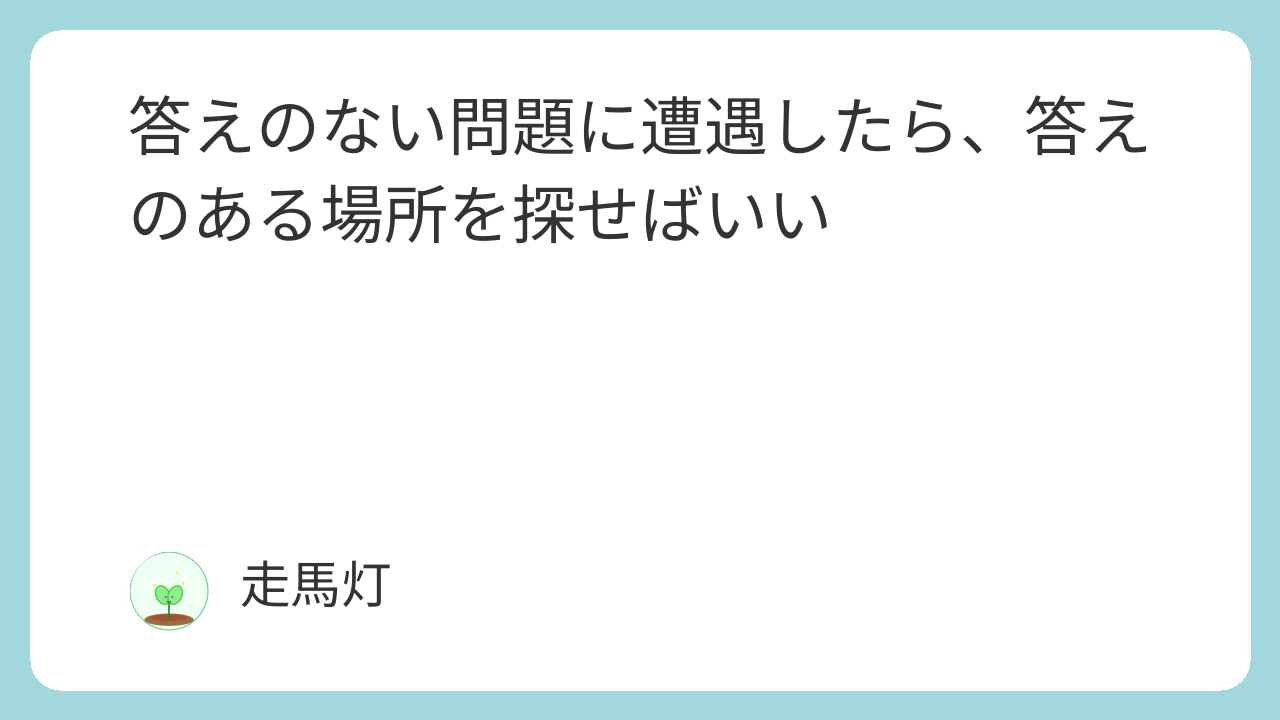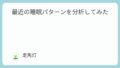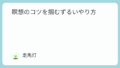知識を増やす=選択肢を増やす
読書とは知識を増やすことであり、知識を増やすことは選択肢を増やすことである。
『読書脳』にはこのような読書のメリットが紹介されており、読んだ時は「本当にそうだな」と納得しました。
というのも、最近、知識を広げることにより選択肢が広がる、ということを実感として理解した瞬間があったのです。
4年前からわたしは数学の勉強をコツコツとやっているのですが、そのなかで複素数という科目を勉強しました。
複素数とは、数学の中で扱う数字の種類で、たとえば自然数は1、2、3…といった正の整数のことです。整数は自然数にゼロとマイナスの数を加えた数です。無理数は分数で表すことのできない数です。
このように、数字には種類があり、複素数はそのうちのひとつです。
複素数との出会い
複素数がわかると、実数だけでは解けなかった問題を解けるようになります。つまり、これまで答えの出せなかった問題に答えを出すことができるのです。
自然数しか知らなかったころには、「3−5」 の答えは「存在しない」でした。
けれど整数を知れば、「3−5」の答えが「−2」と導き出せるようになります。
正直、当時はこれに感動することはありませんでした。子供だったので、毎日が発見の連続で、知らないことの方が多くて、自分には知らないことがたくさんある、という自覚があったのでしょう。だからこそ、答えが導き出せるようになった、という変化に気付けなかった。
けれど、大人になった今は違います。
知っていることが増えて、答えの出せるものが増えました。今思えば、問題の解決策は自分の知る範囲にあるはずだ、という無意識の思い込みがあったのです。
けれど、複素数の勉強を始めてすぐに、それは思い上がりだとわかりました。
高校生の頃、「解はなし」と答案用紙に書いて丸をもらっていた問題は、複素数を使えば解があるのだと知り、衝撃を受けました。
高校生の頃に「解はなし」という答えを書くためだけに何行も計算して、答えがないことを証明していたのはなんだったのか。解はなし、という答えを書いたときの、虚無感のようなものは、複素数を知っていたらなかったのではないか。そう思うと、感動で頭の中がじわっとあつくなり、汗をかいたのを覚えています。
知識を広げれば、答えは見つかる。
この感覚を実感した感動は、大人になってから久々に味わった価値観の変革です。そして、これと同じことが読書でも可能なのです。
人生への応用
知らない事は見つけられない。知らないものは存在しないものだから。だから整数を知らなかったころはマイナスになる数の答えなんて知らなかった。複素数を知らなかったころは「解はなし」という無為な答えを見つけるために何行も計算して証明をしなければならなかった。答えがないことを見つけるための証明なんて虚しいと思いながら。
けれど今なら、マイナスになる数の答えも、実数以外の答えも導き出せます。
仕事で行き詰まった時、友人と喧嘩してどうすればいいかわからなくなった時、よくわからないけれど苦しい時。自分の知っている範囲だけで答えを見つけようとしても、どうしても見つからない時。
そういうときは、もしかしたら答えがないのではなく、答えのある場所を知らないだけかもしれません。
だとしたら、一生懸命答えを探すよりも、まずは答えのある場所を見つけて学ぶ方が近道になります。その答えを知っている人が書いた本は、まさに答えのある場所です。わたしが学んだ複素数の本みたいに、気づきを与えてくれる本が世の中にはたくさんあります。
そしてもっと言えば、答えのある場所をあらかじめ見つけておいて、自分の中にストックしておくのが悩みを最小限にするコツとも言えます。
何か問題に遭遇した時、たくさんの選択肢から探せることは安心感に繋がります。そして、答えを見つける確率が格段に上がります。
読書という解決策
これは『読書脳』にも書かれていることですが、本を読むとそこにはたくさんの解決策やそこに至る考え方や思考法(プロセス)、経験が書かれています。一人の人生では知り得なかった知識が凝縮されていて、知っている数字の種類を増やす、というようなことが本を読む毎に起こるのです。
日常的に読書をすることは、日々「知っている数字の種類を増やす」こと。つまり、「答えのある場所を自分の中にストックする」ことです。
知識のストックは読後に叶うことです。ですが、読書をする過程、つまり、本を選んでその本に知りたいことが書いてあった/書いていなかった、とジャッジするというのを繰り返すことは、答えのある場所を探すスキルを磨くことです。読書は、読む本を選ぶという段階から、その失敗も含めて、無駄なことなんてありません。
読書で得られるメリットは他にも多くありますが、それについては『読書脳』に詳しく書かれているので、ぜひ読んでみてください。
読書を始めるなら『読書脳』読書を加速させるのも『読書脳』
わたしは最近、自分に興味のない分野の本も必ず1冊は手にとるようにしています。そうすることで、知らない用語に触れるようになり、まったく未開拓だった分野でどんな言葉が使われるのか、少しずつですがわかってきました。
実はわたし、投資をやっているのに経済学や政治学に苦手意識があり、ずっと避けていたのです。けれど一時期流行った『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?』という本のレビューで、女性の労働力の透明化、という内容を見て興味が湧き、なんとなく手に取って読んでみました。まったく興味のない分野、なんなら苦手分野なのだから、読み終わるまで時間がかかるだろう。そう思っていたのですが、自分にはない考え方や視点の連続で、面白くて一気に読んだことを覚えています。それからは経済学の本も読むようになりました。おかげで、今では投資関係の話題でよく聞く単語も徐々にわかるようになっています。
これらの経験は『読書脳』に書かれているメリットや、読書後のアウトプットの効果と重なる部分があり、『読書脳』の内容をまさにそう!と納得できる経験にもなっています。
過去の経験に他者からの後押しを得られる。これも読書の醍醐味です。わたしの場合、後押しをえられたらなんとなくでやっていたことも自信を持って続けられる、という性格なので、これからは自信を持って興味のなかった分野、苦手分野の本も手にとってみようと思いました。そしてアウトプットもいっそう力を入れてやっていこうと思っています。
『読書脳』は読書を続けている人にとって今の読書スタイルを後押ししてくれる本だと思います。
そしてなにより、これから読書を始めたいという人にとてもおすすめしたい本です。
『読書脳』は本の読み方、活用方法、選び方まで網羅していて、開いた瞬間から『読書する人』へのレールに乗ることができ、読んだまま実行すれば、自然と本を読み、学び、次の本を探す、ということができる人になれる本です。
個人的には、隙間時間で読んでいい、むしろその方が頭に入る、という内容と、おすすめ本の一覧がとてもよかったと思いました。
わたしは長年、読書はちゃんと時間をとって集中して読まなければいけない、という呪縛に縛られていた人間なので…読書をはじめて1冊目に出会いたい本でした。
これから読書したいという方、ぜひ。